行政書士試験の勉強を進めていく中で、多くの受験生がぶつかる壁があります。
それが「商法・会社法」です。
民法や行政法のテキストだけでも手一杯なのに、さらになんだか小難しい商法や会社法のテキストを前にして、こんな風に思っていませんか?
「範囲が膨大すぎる…」
「条文が複雑で何が書いてあるか分からない…」
「これだけ勉強しても、たった5問しか出ないの?」
その感覚は、至極真っ当です。
行政書士試験における商法・会社法は、学習にかかる時間と得られる点数のバランス、いわゆる「コスパ」が極めて悪い科目だからです。
では、商法・会社法は「捨て問」にして、全てカンで答えても良いのでしょうか?
それとも、他の受験生が手を抜くからこそ「稼ぎ頭」にすべきなのでしょうか?
結論から言えば、どちらも極端すぎます。
合格するための最適解は、「完全に捨てはしないが、深入りもしない。『コスパ最強のつまみ食い戦略』で2〜3問を確実に拾う」ことです。
完璧は目指さないけど、捨てもしないコスパのよい形を目指すのです。
この記事では、多くの合格者が実践している、商法・会社法との最も賢い付き合い方を徹底解説します。
1. なぜ「商法・会社法」は嫌われるのか?コスパ最悪の現実
戦略を立てる前に、敵を知りましょう。
なぜここまで商法・会社法は受験生を苦しめるのでしょうか。その理由は明確です。
① 圧倒的な「範囲の広さ」対「配点の低さ」
行政書士試験の配点は300点満点。そのうち、商法・会社法の配点は以下の通りです。
- 商法:1問(4点)
- 会社法:4問(16点)
- 合計:5問(20点)
全体のわずか約6.6%に過ぎません。商法にいたってはわずか1問しかありません。
一方で、会社法の条文数は約1,000条あります。これは民法(約1,050条)とほぼ同規模です。
民法は76点の配点がある重要科目ですが、商法と会社法はその1/4以下の配点しかありません。
同じ努力をして得られるリターンがあまりにも少ない。これが「コスパ最悪」と言われる最大の理由です。
② とっつきにくさと複雑さ
民法は「隣の家の騒音トラブル」や「遺産相続」など、日常生活でイメージしやすいテーマを扱います。
しかし、特に会社法は「取締役会の決議要件」や「株式の発行手続」など、企業の法務担当でもない限り、実生活で馴染みがないテーマばかりです。
さらに、条文が長く、相互に参照し合う構造になっているため、初学者が独学で読み解くのは非常に困難です。
2. 「完全捨て問(全問サイコロ)」が危険すぎる理由
「そんなにコスパが悪いなら、いっそ勉強せずに全部『3』にマークすればいいのでは?」
そう考える受験生も少なくありません。実際、それで合格した人もいるでしょう。しかし、近年の難化する行政書士試験の傾向を考えると、「完全捨て」はリスクが高いです。
① 「180点の壁」はギリギリの戦い
行政書士試験の合格ラインは180点(6割)です。
合格する多くの受験生が、民法や行政法で多少の取りこぼしをし、基礎知識で足切りを回避し、結果として記述を除いて150点〜190点あたりに着地します。
しかし、もし民法や行政法が難化して思うように得点できなかった年だったらどうでしょうか?
あと1問、あと4点足りずに涙を飲むことになります。
そんな時、商法・会社法で拾った「たった1問」が、合否を分ける命綱になるのです。
② 意外と「取れる問題」も混ざっている
ここが重要なのですが、商法・会社法の5問すべてが難問奇問というわけではありません(難問奇問がたまに出ることもありますが…)。
5問中、1〜2問は、基本的なテキストに載っているレベルの「知っていれば秒で解ける問題」が出題されます。
これをみすみす逃すのは、非常にもったいないことです。
3. 合格者の常識!「コスパ最強のつまみ食い戦略」とは
それでは、どうすれば良いのでしょうか。
目指すべきゴールは、「満点(5問正解)は最初から狙わず、最小限の努力で2〜3問を拾う」ことです。
そのための具体的な戦略は以下の通りです。
戦略の基本方針
- 深入り厳禁:細かい例外規定やマイナー条文は無視する。
- 頻出分野に一点集中:出る可能性が高い分野「だけ」やる。
- 過去問主義:過去問で問われた知識を中心にインプットする。
4. ここだけやればOK!具体的な学習優先順位
「つまみ食い」と言っても、どこをつまめば良いのでしょうか。
優先順位が高い順に紹介します。ここだけやれば十分お釣りが来ます。
【最優先】商法総則・商行為(絶対に落とせない1問)
ここは絶対にやってください。コスパが良い分野です。
条文数が少なく、内容も「商人」「商号」「商業使用人」など、比較的イメージしやすいものが多いです。
例年、ここから1問出題されますが、難易度が高いわけではありません。
「たとえ1問だけでも商法は取る」という戦略は有効です。ここを確実に取れば、これだけで4点確保です。
【優先度高】会社法:設立
会社法の最初の関門ですが、実は狙い目です。
「発起設立」と「募集設立」の手続きの流れ、定款の記載事項など、覚えることは多いですが、一度流れを理解してしまえば得点源になります。
出題頻度も高く、比較的素直な問題が多い分野です。
【優先度中】会社法:機関(株主総会と取締役会のみ)
会社法で最もボリュームがある「機関」ですが、全てをやる必要はありません。
会社法に時間をかけすぎない方針でいくのであれば、以下の2点に絞りましょう。
- 株主総会:招集手続き、決議要件(普通決議・特別決議の違い)
- 取締役・取締役会:任期、取締役会の権限
これらは行政書士になったあとの実務でも重要であり、試験でも頻出です。
逆に、監査役、会計参与、委員会設置会社などの細かい規定は、余裕がなければバッサリ捨てても構いません。
【優先度低】株式、資金調達、組織再編など
「株式の内容」「新株予約権」「合併・分割」などは、非常に複雑で難解です。
司法書士試験や公認会計士試験レベルの知識が問われることもあります。
行政書士試験においては、これらに時間を割くくらいなら、その時間を行政法の復習に充てた方が合格に近づきます。
とはいえ、まったく取り組まなくてよいというわけではなく、「過去問に出てきた知識はチェックする」ことはきちんとしましょう。
5. いつ勉強する?ベストなタイミング
商法・会社法は、勉強するタイミングも重要です。
絶対にやってはいけないのが、学習初期(春頃)に気合を入れて勉強することです。
なぜなら、忘れてしまうからです。
商法・会社法の知識は、体系的な理解よりも「単純暗記」の要素が強いため、記憶の維持が難しいのです。
おすすめのスケジュール
- 〜8月まで:ノータッチでOK。民法と行政法の基礎固めに全力を注ぐ。
- 9月以降(直前期):民法・行政法の目処が立ったら、少しずつ「つまみ食い」を開始する。
- 試験1ヶ月前〜直前:絞り込んだ頻出分野の「詰め込み暗記」を行う。
商法・会社法は「短期記憶勝負」の科目と割り切りましょう。前半ではなく後半に詰め込んで記憶があるうちに本試験に臨むのです。
まとめ:商法・会社法は「優秀な補欠選手」
行政書士試験における商法・会社法は、決して主役(稼ぎ頭)ではありません。主役はあくまで民法と行政法です。
しかし、完全に戦力外(捨て問)にするには惜しい存在です。
上手に付き合えば、主役が調子を崩した時に助けてくれる「優秀な補欠選手」になり得ます。
「全部やらなきゃ」という完璧主義を捨て、「ここだけは拾う」という割り切りを持つこと。
それが、コスパ最強の会社法攻略術であり、行政書士試験合格への賢い戦略です。
限られた時間を有効に使って、合格を勝ち取りましょう!
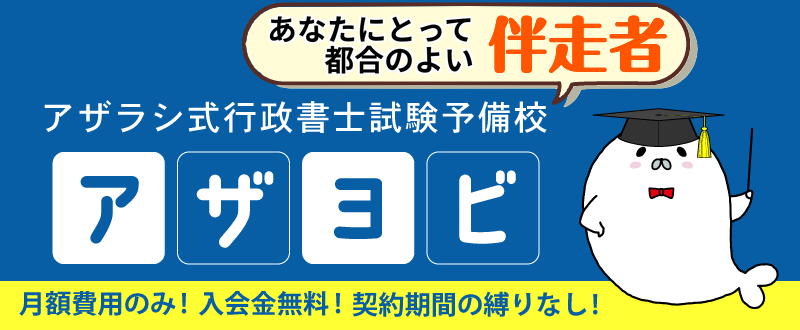
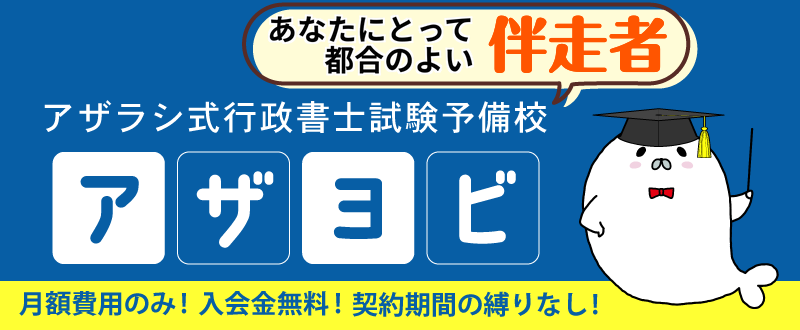

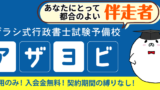
コメント