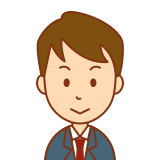
司法試験合格を目指しながら行政書士試験を受ける人ってどのくらいいるの?
行政書士試験の勉強をすすめるにあたって、このような疑問をもつ人は多いことでしょう。実際のところ行政書士試験の受験生の中に「司法試験/予備試験組」がどの程度いるのでしょうか?
実は、統計にはハッキリと表れませんが、「司法試験/予備試験組」は「隠れた巨大勢力」といえる存在です。司法試験・予備試験の受験生(法曹志望者)たちは、行政書士受験生の中でも一大勢力になっているのです。
データと受験生心理を分析すると、約3,000人〜4,000人規模の司法試験勢が参戦してくると推測されます。
※令和6年度(2024年度)試験を元にした推計値。

弁護士を目指すような人たちが、なんで行政書士試験を受けるの?。
このように思う方もいるかもしれません。この記事では、「司法試験/予備試験組」がなぜ行政書士試験を受験するのか、そして私たち一般の行政書士受験生は、この「一大勢力」たちにどうやって立ち向かい、合格を勝ち取ればいいのかを徹底分析します。
1. なぜ今、「司法試験組」が行政書士試験を受けるのか?
司法試験(予備試験)と行政書士試験。この二つの試験は難易度は違いますが、実は「親和性」が非常に高い試験です。
主な理由は以下の2点です。
① 試験科目が「丸かぶり」している
行政書士試験の主要科目である「憲法」「民法」「商法(会社法)」「行政法」。
これらはすべて、司法試験でも必須の科目です。つまり、彼らにとって行政書士試験の法令科目は、「普段の勉強の延長線上」にあります。新たに勉強し直す必要がほとんどありません。
② 「資格」という保険が欲しい
司法試験の登竜門である「予備試験」の合格率は約3〜4%。極めて狭き門です。何年も勉強を続けているのに「無資格」という状態は、精神的に非常にプレッシャーがかかります。
「とりあえず行政書士資格を取って、法律家としての自信をつけたい」
「就職活動やアルバイトのために、履歴書に書ける国家資格が欲しい」
こうした「実益」と「精神安定剤」を求めて、行政書士試験を併願するケースが非常に多いのです。
2. 【アザヨビによる試算】流入してくる「ガチ勢」は何人いる?
それでは、具体的にどのくらい司法試験/予備試験組の人数が流れてくるのでしょうか。
公開されている令和6年のデータから推測してみましょう。
推測の根拠データ
- 司法試験予備試験の受験者数:約13,000人
- 法科大学院生等の数:数千人規模
予備試験受験生(約1.3万人)の中には、記念受験層や、すでに合格している上位層も含まれます。
最も行政書士試験を併願するのは、「合格を目指して数年勉強しているが、まだ結果が出ていない中間層」と推測されます。
以上から、過去の傾向や受験生の動向から、予備試験受験生の約25%が併願すると仮定します。
13,000人 × 25% = 3,250人
ここに、法科大学院生(ロースクール生)からの流入(約500〜700名と推測)を加えると……
合計:約3,700人 〜 4,000人
行政書士試験の受験者数が約6万人だとすると、人数の割合としては約6〜7%に過ぎません。しかし、問題なのは「数」ではなく「質」です。
彼らは長い時間をかけて、レベルの高い法律知識と向き合っている法律のプロ予備軍です。合格率が10〜12%程度の行政書士試験において、この「4,000人の猛者」が上位を占有してしまう可能性は高いです。
3. 行政書士試験制度の改正は彼らにとって「追い風」が吹いている
さらに、司法試験/予備試験組にとって有利な状況が生まれています。それは行政書士の試験制度の変更です。
これまで、司法試験組が行政書士試験で不合格になる最大の要因は「一般知識(政治・経済・社会)」でした。
法律は完璧でも、クイズのような政治経済の問題で足切りを食らって涙を飲む……というケースは多かったのです。しかし、令和6年度から「一般知識」は「基礎知識(行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令を含む)」へと変更されました。つまり、「あやふやなクイズのような一般常識」が減り、「法律知識」で解ける問題が増えたのです。
これは、法律特化で勉強している彼らにとって、足切りのリスクが減り、非常に戦いやすい環境になったことを意味します。
4. 一般の受験生はどう戦えばいいのか?「勝機」はここにある
以上を読んだ行政書士専業の受験生のみなさんは…
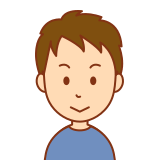
そんな猛者たちが来るなら、勝てるわけがない…
と思うかもしれません。
しかし、簡単に諦める必要はありません。司法試験/予備試験組にも弱点はありますし、行政書士試験には特有の「合格のツボ」があります。
なにより行政書士試験は、合格ラインを超えた点数を獲ればよい国家試験です。私たち一般の受験生が勝つための戦略は、以下の3つです。
① 「行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法」で差をつける
司法試験組は、憲法や民法はプロ級ですが、行政書士特有のマイナー法令(行政書士法など)の対策はおろそかになりがちです。
彼らが「常識で解けるだろう」と高をくくっている間に、私たちはここを完璧に仕上げて点数を稼ぐことができます。
② 記述式は「深入り」しない
法律を知りすぎている彼らは、記述式問題において「難しく考えすぎてしまう」傾向があります。
行政書士試験の記述式は、条文のキーワードを正確に書くことが求められます。学説や高度な理論を展開する必要はありません。
「基本に忠実に、聞かれたことだけを書く」。この姿勢なら、十分に互角以上に戦えます。司法試験に臨むような高度な法律知識が求められているわけではないのです。
③ 「Aランク問題」を絶対に落とさない
これが最も重要です。
行政書士試験は、誰かが落ちることで誰かが受かる競争試験の側面もありますが、基本的には「取るべき問題を落とさなければ受かる試験」です。
司法試験組が難しい問題を正解しても、配点は同じです。難しい判例や理論に手を出す必要はありません。
「受験生の50%以上が正解する基本問題(Aランク問題)」を1問も落とさない精度。
これさえあれば、相手が誰であろうと合格点(180点)には必ず届きます。
5. 行政書士試験は絶対評価「180点以上を獲得すれば合格できる」
そもそも行政書士試験は絶対評価で180点以上を獲得できれば合格できます。
絶対評価ということは、司法試験・予備試験組と比較されて優劣をつけて合否判定されるわけではないのです。
司法試験・予備試験組は日頃から、より高いレベルで法律の勉強に取り組んでいます。そんな彼らに勝つ必要はありません。勝つ相手は司法試験・予備試験組ではないのです。行政書士試験専業の受験生が勝つべき相手は、行政書士試験です。
司法試験・予備試験組よりも高得点をとる必要はないのです。目指すべきは合格点である180点以上をとることだけです。
合格点を獲得できれば、それは行政書士試験に勝利したことになります。司法試験・予備試験組に勝とうとするのではなく、行政書士試験に打ち勝つ気持ちをもって戦いましょう!
まとめ:相手を知れば、恐れる必要はない
あくまでも推定ではありますが、約4,000人の司法試験・予備試験組が参戦してくるのが脅威となるのは事実でしょう。しかし、彼らの存在を過度に恐れる必要はありません。
むしろ、「今年はレベルの高い受験生が多いから、基礎をおろそかにしたら命取りになる」という良い緊張感に変えてください。彼らは「法律のプロ予備軍」かもしれませんが、彼らと一緒に合格を勝ち取ることは十分に可能なことなのです。
行政書士試験に特化した最短ルートの対策を淡々と続けていけば、最後には合格証書を手にすることができます。ライバルは多いですが、やるべきことは変わりません。ぜひアザヨビを活用して、基礎を大切に、コツコツと積み上げていきましょう!
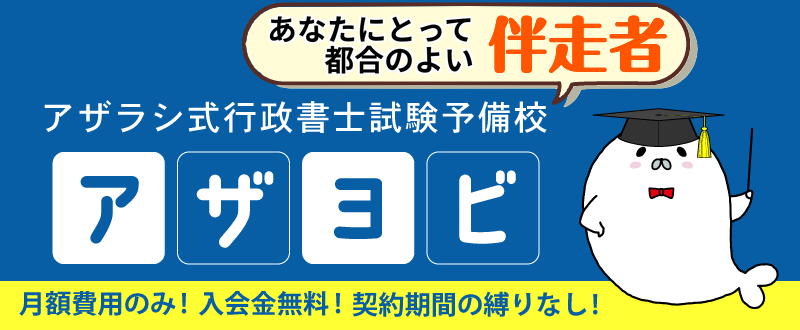
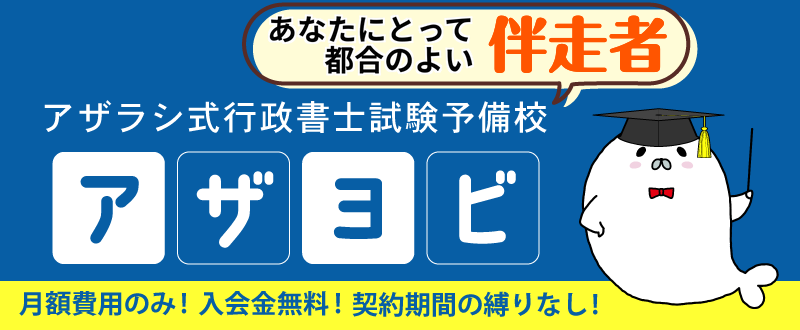

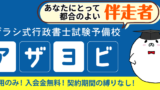
コメント